大湊神社 御清塩

大湊神社 御清塩 (おおみなとじんじゃ おきよめしお)
「雄島」の鎮座する福井県坂井市三国町安島。
その海水を「志野製塩所」で焚き上げて、作られた塩です。
その後、「大湊神社」でお祓いし封入いたしました。
お供え・盛塩・清めの塩としてご使用ください。
 |
 |
※ 原 料;三国町安島の海水
※ 容 量;40g (大容量をお求めになられる際は、ご連絡ください。)
※ 頒布開始;令和6年4月20日~
※ 初穂料;500円
「御清塩」について
「塩」は、古来より食用だけではなく、様々な儀式に用いられてきました。
それは塩の持つ強力な浄化作用に由来します。神代の時代から、海水に浸かることで身体を清める「禊(みそぎ)」も行われてきました。 そして「盛り塩」をすることにより、邪気を祓い、場を清め、清浄を保ち、生命力を更新し、良い気を生み出すと考えられています。 これらの効能を考えれば、加工された食塩ではなく、生命の源である海から得た塩が最も適しているのではないでしょうか。
三国の古代製塩について
北陸の製塩は古墳時代前期の末頃、若狭に始まり、平安時代頃まで三国や能登半島に約200ヶ所を数える遺跡が確認されております。
荒磯遊歩道の東尋坊から米ケ脇地区に向かう途中の断崖下で、ナイフ形旧石器が出土し、この場所を「西下向遺跡」と呼んでいますが、 その近い場所に「藻取浜遺跡」があります(藻取浜は、この地区の字名としても残っています)。 その名の通り、古い時代この場所で、海藻に海水をかけ、その藻を焼き、灰を海水で溶き、土器で煮詰めて製塩を行ったと考えられています。
( ※ 但、この「大湊神社御清塩」は、煮詰めてはいますが、海藻を使った製法では作っておりません。)
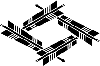
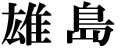 (Oshima)
(Oshima)